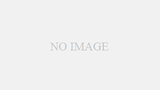この記事では、「菖」の読み方を分かりやすく説明していきます。
くさかんむりに昌で「菖」の読み方
「菖」は音読みでは、「ショウ」と読みます。
また、訓読みで「しょうぶ」と読みます。
「菖」の意味や解説
「菖」とは、植物の「ショウブ」、「アヤメ」、「ハナショウブ」のことを表しています。
「ショウブ」は、ショウブ科ショウブ属の多年草で、独特の芳香があります。
漢字では「菖蒲」と表記します。
開花時期は5月から7月頃で、黄緑色の小さい花が咲きます。
「ショウブ」は薬用に利用されています。
古名は「あやめ・あやめぐさ」で、万葉集にもあります。
また、端午の節句の菖蒲湯としても知られています。
「アヤメ」は、アヤメ科アヤメ属の多年草で、「菖蒲・綾目・文目」の漢字表記があります。
5月から7月頃に、6個の花被片の紫色の花が咲きます。
二十四節気七十二侯では、夏至の次侯に「菖蒲華(あやめはなさく)」として登場します。
「ハナショウブ」は、アヤメ科アヤメ属の多年草で、「ノハナショウブ」の改良園芸種です。
5月から7月頃に花が咲き、紫、白、ピンク、黄、青などのさまざまな色があります。
漢字では「花菖蒲」と表記します。
「菖」の熟語での使い方や使われ方
・『六菖十菊』【りくしょうじゅうぎく・ろくしょうじゅうぎく】
適切な時期が過ぎてしまい、役に立たないもののたとえです。
・『十日の菊、六日の菖蒲』【とおかのきく、むいかのあやめ】
「六菖十菊」と、同じ意味で、時期が遅れてしまって、役立たないことを意味しています。
・『いずれ菖蒲か杜若』【いずれあやめかかきつばた】
どちらも素晴らしく、甲乙つけ難いことを表しています。
まとめ
「菖」は「くさかんむり」に「昌」と書きますが、「くさかんむり」は漢字の冠の一つで、「草冠」と漢字表記します。
また、「昌」は音読みで、「ショウ」、訓読みで「さか(ん)」と読んで、「さかん」、「明らか」、「栄える」などを表しています。
言葉の読み方や意味を知ることで、より適切に使えるようになるでしょう。