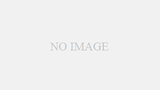この記事では、「儺」の読み方を分かりやすく説明していきます。
にんべんに難で「儺」の読み方
「儺」の読み方は、音読みでは「な」、「だ」があります。
また、訓読みでは「おにやらい」と読みます。
「儺」の意味や解説
「儺」は「おにやらい」と読みます。
「鬼遣」と記載することもあります。
さらに「儺祭 (なのまつり)」などと呼ばれることもあります。
厄病を追い払う儀式として知られています。
大陸から輸入された儀式とされていて、平安時代には大みそかに行われていました。
「方相氏」と呼ばれる役職を持つ人が、都などを襲う鬼を追い払う役割を担当したとされています。
この儀式が、節分に豆まきをするという、現在にも続く儀式につながっていると言われています。
今でも、古式を復活させて、「儺」を行っている寺社もあると言います。
また、「儺」は、子供たちの遊びである、「鬼ごっこ」の起源という説もあります。
「儺」の熟語での使い方や使われ方
・『追儺』【ついな】
「追儺」は、「おにやらい」と同じ意味があり、悪鬼を追い払う儀式のことを指します。
この当時の鬼とは、疫病のことを指し、原因不明の伝染病を追い払うために行った儀式とされています。
・『大儺』【たいな】
「大儺」は、「大々的に鬼を追い払うこと」という意味があります。
また、「おにやらい」において、鬼を追い払う役割を担う人を、こう呼ぶことがあります。
・『小儺』【しょうな】
「おにやあい」の儀式で、「鬼を追い払う役割を持つ大儺に従って、内裏を駆け回る子供」のことを意味します。
まとめ
「儺」は「おにやらい」と読むことが分かりました。
現代の節分の儀式である豆まきにつながる言葉になります。
基本的に現代では、一般的に使われることが少ない言葉のため、今回初めて知る言葉という人が多いのではないでしょうか。