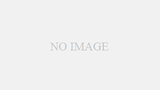にんべんに寺と書く「侍」は何と読みどのような意味を持つのでしょうか。
今回は、「侍」の読み方と意味について解説します。
にんべんに寺で「侍」の読み方
「侍」の読み方は音読みでは「ジ」「シ」、訓読みでは「さむらい」「はべ?る」「さぶら?う」です。
「侍」の意味や解説
「侍」とは、「身分の高い人の下に仕える人」あるいは「誰かに支えている武士階級の人」を意味する言葉です。
元々は高貴な身分を持つ人に仕え身の回りの世話をしたり身近で警護にあたったりする側仕えを指す言葉でしたが、時代が下るにつれ誰かの下に仕えて働く人全般を指すように意味が変化します。
古代から中世にかけては官人や軍人などを指す言葉として使われていましたが身分階級が明確になると武士の身分呼称として使われるようになり貴族や官人に対しては用いられなくなります。
武家社会になると主君に仕える武士を表す言葉として使われるようになり、主に浪人や野武士など主君を持たない無頼の者と士官している者を区別する意味で用いられる言葉です。
現代では誇り高い生き方や主君に対する忠誠心など精神性や生き様に重きを置いた意味合いで用いられます。
「侍」の熟語での使い方や使われ方
・『侍魂』【さむらいだましい】
「侍が目指す高潔で誇り高い生き方」のことです。
立派な侍の間に共通して見られる考え方や態度を表す言葉で具体的な形を持つものではなく生き方の基準となる信念を表す言葉です。
・『寺侍』【てらざむらい】
「寺に仕える侍」を指します。
江戸時代には格式の高い寺社が私的に侍を雇い寺の仕事を任せていました。
そのような主君として武士に仕えるのではなく寺に雇われて働く武士を指す言葉です。
寺の警護や書物の管理、子どもたちに対する読み書きそろばんの教育など仕事内容は多岐に渡ります。
まとめ
「侍」と武士を同じ意味だと考えている人も多いのですが誰かに支えているかいないかで明確に区別されます。
混同しやすい言葉なので正しい意味と読み方を覚えておきましょう。