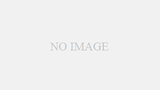鬼の副長「土方歳三」の晩年とは?
この記事では土方歳三の死に際、そして晩年について解説していきます。
「土方歳三」とは?簡単に説明
司馬遼太郎氏の小説『燃えよ剣』の映画化が行われ、主役の土方歳三は岡田准一氏が演じ2021年10月から公開されています。
原作小説が発表された1960年代末ですが、それ以前より新撰組で一番人気だったのが土方歳三です。
鬼の副長と呼ばれ、単純な剣技では沖田、近藤に劣るものの総合的な“強さ”では一番であると言っていいでしょう。
新撰組、そして幕末の五稜郭、蝦夷島政府でも実質的な指揮官として、現場で組織を動かし、人を廻す役割を果たしました。
それは時に大胆不敵、時に小心翼々な策を見せ、右腕以上の活躍を見せています。
「土方歳三」の晩年
新撰組のなかで武勇に優れ、現場を動かし時には汚れ役も果たしていた土方でしたが、急激な時代の荒波に翻弄され、飲み込まれていきます。
錦の御旗が新政府軍に掲げられ、鳥羽伏見の戦いでは年末に重傷を負った近藤勇、病に直れた沖田総司の分まで奮戦するも叶いません。
江戸に帰り、内藤隼人の名で臨んだ甲州勝沼の戦いも大敗、さらには会津出立前の流山で近藤を喪うこととなるのでした。
自身は勝海舟に近藤の除名嘆願を求めた後に幕府軍と合流します。
下野国での一連の戦いで負傷し、会津戦争では斎藤一と袂を分かち、その先の仙台藩で榎本武揚と合流。
最終決戦の地、五稜郭へと流れ込むこととなります。
「土方歳三」の死に様
蝦夷共和国を成立させるも、開陽丸を失った時同様に運のなさが響いて宮古湾海戦でも敗退を喫します。
1869年5月18日にいよいよ新政府軍が上陸、防戦に奮闘するも形勢を逆転させることは叶わぬまま月日は流れていくのでした。
約1ヶ月後の6月20日、新政府軍が函館を総攻撃を開始。
厳しい戦局のなか、包囲された弁天台場の手勢を救うべき前線へと向かいます。
ここで蟠竜丸が朝陽丸を撃沈したことを見てさらに奮起、兵士を叱咤し一本木関門で新政府軍を迎え撃つのでした。
しかし乱戦の中、銃撃の傷を負い落馬、それにより絶命したと言われています。
1869年6月20日没、享年35のことでした。
「土方歳三」の死に様の信憑性
斎藤一や永倉新八実在した新撰組の生き残り組以外で創作物では明治の世も生き残っていたとされることも多いのが土方歳三です。
陸軍奉行添役を務めた大野右仲が知らせを受けた時には絶命していたとされています。
その後本陣である五稜郭から戦死した一本木関門まで遺体を引き取りに行ったのが、将軍家御庭番であった小芝長之助。
とここまでは記述は残っていますが、埋められた場所が確定していないのに加え、辞世の句も候補はあるもののはっきりしていません。
これが源義経、羽柴秀頼、島左近などと同様生き延びた説を生んだ原因とも言えるでしょう。
まとめ
土方歳三は最前線で指揮をとっている最中に銃撃を受けて死亡しました。
前線で戦っていたものの遺体は回収され、五稜郭の何処かへと埋められたもののその所在はわからないままです。
これが憶測と想像を呼んで土方生存説に繋がることになるのでした。